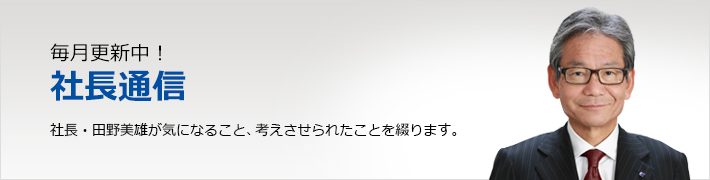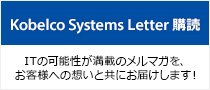2025年04月01日
駅伝という「個人競技の団体戦」の意義
~専門能力を伸ばすための組織~
 今年4月から開催される日本国際博覧会(大阪・関西万博)の記念イベントの一つとして3月16日、万博記念公園から大阪・関西万博会場までの7区間54.5kmでACN EXPOEKIDEN 2025が開催されました。大学と実業団のトップチームが一緒に参加する駅伝大会として注目を集めましたが、結果はトヨタ自動車が1区からトップを譲らず優勝。今年1月の第101回箱根駅伝で2年連続8度目の総合優勝を大会新記録で果たした青山学院大学は7位という結果でした
今年4月から開催される日本国際博覧会(大阪・関西万博)の記念イベントの一つとして3月16日、万博記念公園から大阪・関西万博会場までの7区間54.5kmでACN EXPOEKIDEN 2025が開催されました。大学と実業団のトップチームが一緒に参加する駅伝大会として注目を集めましたが、結果はトヨタ自動車が1区からトップを譲らず優勝。今年1月の第101回箱根駅伝で2年連続8度目の総合優勝を大会新記録で果たした青山学院大学は7位という結果でした
特に10人がそれぞれ約20㌔を走ってタスキをつなぐ箱根駅伝では、距離も長く選手は低体温症などでフラフラになることも多々あります。それでも何とか最後まで走り切ろうと必死に前を向きます。「チームのため、仲間のため」という強い思いが選手を突き動かします。
また、選手の中には卒業後も長距離ランナーとしてマラソンやトラック競技などで世界を目指す者もいれば、箱根駅伝を最後に競技から引退を考えている者もいます。個人個人が将来全く違うキャリアを目指しながら、チームとして共通の目標を追求する、そんな微妙なバランスの中での競技と言えます。
この冬、青山学院大学の箱根駅伝優勝メンバーもそれぞれ違った思いを持ってマラソンを走りました。5区の区間新記録をマークした若林宏樹選手(4年)は2月2日の別府大分毎日マラソンで初マラソン日本最高、日本学生新記録の2時間6分7秒で日本人トップの2位となりました。このマラソンを引退レースと公言していた若林選手は「これが最後と思って走りました。これでやめるからこそ出たタイムだと思います」と話しました。
すると、それから1か月もしない同24日の大阪マラソンでは黒田朝日選手(3年)が、この記録を2秒更新。初マラソンで日本学生新の2時間6分5秒で6位に入りました。「同じチームの先輩の若林さんが走れたということは自分にもできると思って、自信を持ってスタートに立てました」と感謝。また、この日は19日に悪性リンパ腫のため死去したチームメート・皆渡星七さん(享年21)の告別式があり、シューズの厚底部分に「皆渡星七パワー!」と手書きで入れて、仲間への思いも胸に好走しました。苦しい時に支えとなるのはそういった仲間からの力なのでしょう。
3月2日の東京マラソンには太田蒼生選手(4年)が出場。最初から攻めた走りを続けたため低体温と低血糖により36㌔で途中棄権しましたが、「世界のレベルを知れて良い経験ができました。3年後には五輪で勝ちます」と話しました。もし駅伝だったら棄権覚悟で自分の限界に挑むような走りは絶対にしなかったでしょう。団体戦で背負う責任から解放され、自分自身が抱く将来に向けて積極的にチャレンジする姿が印象的でした。
同じチーム内で良い競争関係が出来上がると、ライバルから学び、刺激を受けることができます。それによって互いに切磋琢磨しながら能力を向上させるだけでなく、苦しい時には精神的な支えにもなります。
仕事の現場でも同じです。同じ職場の同僚との切磋琢磨は、より質の高い仕事を生み出すモチベーションの源泉となり、結果的に自身の能力向上に加え、組織全体のパフォーマンスも向上させることになります。また、難しい課題に挑む時は、頼れる仲間の存在によって襲ってくる不安を払拭し背中を押してくれるでしょう。
近年、仕事の専門分化が加速しており、特定分野で高い専門スキルを持ったスペシャリストを目指す人が増えています。そのような専門スキルを伸ばすための場として、あえて企業の中に身を置くことも有効な手段の一つではないでしょうか。特に若者にとって目指すべき専門領域でのロールモデルが所属組織の中で身近に存在することは、必ず成長の糧となり能力向上を早めることにつながると思います。
昔は「会社」が団体戦を勝利するために「個人」を強化するという人材育成が主流でした。しかし、これからは「個人」の成長のために「会社」が仲間と一緒に団体戦を戦う職場を提供する、そのような考え方が大切になってきていると感じています。いかに個人のキャリア志向と組織目標とのバランスをとって人材を育成していくか。その仕組みを構築することが優秀な人材を集める企業となるための絶対条件なのです。
2025年4月
最新の記事
年別
ITの可能性が満載のメルマガを、お客様への想いと共にお届けします!
Kobelco Systems Letter を購読