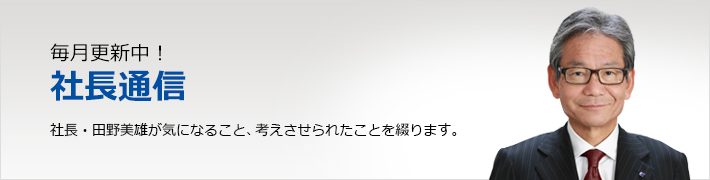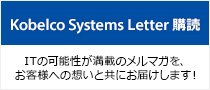2025年03月01日
「ルールの隙間を突く」発想の大切さ
~イノベーション人材を育てる~

日本で最もポピュラーなスポーツの一つである野球においても、試合では投げる、打つなどの技術を競い合うのはもちろんですが、できることはそれだけではありません。
例えば、「隠し球」はその代表例の一つでしょう。走者にわからないように内野手がボールを隠し持ったまま守り、走者が塁を離れた途端に内野手が走者にタッチしてアウトにする。これは走者が『投手がボールを持っているはずだ』と思い込んで守備側の動きに惑わされたことで起こったミスであり、それを誘発するために考えられたプレーなのです。
また以前は二塁走者が捕手の構えなどを見て、打者に対して投手が投げようとしているコースを教えることは当たり前に行われていました。しかし、外野の客席からのサイン盗み疑惑なども問題となり、現在では二塁走者の少しの怪しい動きも許されなくなっています。
高校野球では今でも語り継がれる1998年夏の準々決勝、PL学園高等学校(以下、PL学園)vs横浜高等学校の延長17回の死闘の舞台裏で行われていたプレーが話題になりました。PL学園の三塁コーチャーが捕手の構えから投手の球種を読み取り、ストレートの時は「行け」、変化球は「狙え」と大声で叫んで味方打線に伝えていたのです。このことはNHKでも番組で紹介され「高校生離れした頭脳戦」として驚きをもって取り上げられました。しかし、これも「卑怯だ」、「高校生らしくない」との声が上がり、サイン盗みとともに禁止されました。
2013年夏の大会では、花巻東高等学校のある小兵の選手がカット打法でファウルを打ち続けました。鳴門高等学校戦では5打席で相手投手に41球も投げさせました。際どいボールをファウルするのは高等技術のはずですが、大きな話題となったこともあり高野連は「自分の好む投球を待つために、打者が意識的にファウルするようなカット打法」に対して高校野球独自のルールに当てはめて、審判がバントと判断したら(スリーバント失敗で)三振になると注意喚起し、それ以降この打法は使われなくなりました。
競技にはルールがあり、ルールには必ず隙間があります。「ルールの隙間を突く」とは、ルールには明記されていないけれども当たり前の「常識」として認識されている盲点を利用することです。その隙間をどのように見つけて、どのように利用するかが勝利への鍵になるのです。
ビジネスでも同じです。昔から「常識を疑え」という言葉があります。当たり前と思われている固定観念や既成概念にとらわれず、「常識」に疑念を持って改革を実行することがビジネスには有効だと言われてきました。
実際にUberやAirbnbは、国や地域によっては違法もしくは違法ぎりぎりのグレーゾーンであった「白タク」や「部屋貸し」といったルールの隙間に踏み込み、今や世界を変えてしまうほどのビジネスに成長しました。「なるほどその手があったか」、「どうして気付かなかったのか」と思われることが、まさにイノベーションなのです。
今まで時代を変革してきた先駆者たちは、ルールを最大限に活用して最大の成果を得るためにルールの隙間まで踏み込んで行動してきています。一方、日本人はルールを厳格に守り常識的に行動しがちです。そのため柔軟な発想ができず、ルールの隙間すなわちグレーゾーンと言われる領域に踏み込めなくなっているのではないでしょうか。
もう一つの問題は、前述の例のようにルールの隙間を突いたプレーのほとんどが「禁止」という結末になっていることです。当時は認められていても、その後フェアプレーの精神に反するなどの理由から禁止されています。なぜ、球種を盗まれないような新しいテクニックの習得を奨励しなかったのか。なぜ、カット打法が通用しないぐらいの投球術を身につけることに向かわせなかったのか。保守的な思考でイノベーションの芽を摘み取ってしまう日本社会の危うさが、野球を通して見え隠れしているように思えてなりません。
自由な発想で新たなテクニックや戦術が生まれれば、それに対してさらに高度なものを編み出して仕掛けていく。そのような小さなイノベーションの繰り返しが競技全体のレベルアップにつながるのです。
近年、VUCAと言われる予測困難な時代へと変化しつつあり、今まで当たり前であった常識が一瞬で覆ることもあるでしょう。不確実な時代において、企業は自由な発想でルールの隙間を突いて、何かをつくり、ルールごと変えてしまうようなイノベーション人材を育成しなければなりません。
まずは経営者が「なるほどそんな面白い手があるのか」と新しいアイデアの創出を奨励し、組織全体で育んでいくような風土に変革していくことが必要ではないかと思っています。
2025年3月
ライター

代表取締役社長
瀬川 文宏
2002年 SO本部システム技術部長、2008年 取締役、2015年 専務執行役員、2017年3月より専務取締役、2021年3月代表取締役社長に就任。現在に至る。
持ち前のガッツでチームを引っ張る元ラガーマン。
最新の記事
年別
ITの可能性が満載のメルマガを、お客様への想いと共にお届けします!
Kobelco Systems Letter を購読