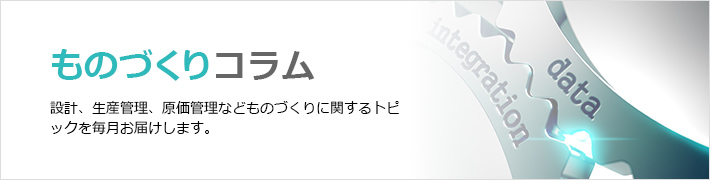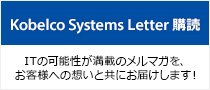2025年03月01日
次世代ものづくり、インダストリー5.0で競争力を高める
今やDX推進はどの産業においても優先事業課題ですが、製造業においてはDXが本格化する以前からインダストリー4.0(第4次産業革命)として、デジタル化の取組みが始まっていました。つまり製造業に限定すると、DX≒インダストリー4.0と見なすことができます。これまで約15年間、世界の製造業各社が範としてきたインダストリー4.0ですが、数年前から次世代のインダストリー5.0が提唱されています。今回はインダストリー5.0に見る、次世代ものづくりの在り方と日本製造業の対応について考察します。
これまでのインダストリー4.0とその限界
インダストリー4.0は2011年にドイツ政府が提唱した国家戦略ですが、同様の取組みが同じ製造立国の日本や中国、米国など世界中の国々において第4次産業革命として取り組まれてきました。IoT、ビッグデータ処理、AIを始めとしたデジタル技術を活用し、スマートファクトリー化することなど、主に自動化/効率化に焦点が当てられてきました。そのため、人間の役割を軽視し、労働者のスキルや創造性が十分に活かされないという課題がありました。加えて、環境への影響を最小限に抑えるだけで積極的な環境保全を行うものではないこと、コロナ禍などの予期せぬ事態に柔軟性がないことが、インダストリー4.0の限界となっています。インダストリー5.0が目指す次世代製造
インダストリー4.0の限界を補完し、より包括的で持続可能な次世代の製造を実現するのがインダストリー5.0です。欧州全体の産業政策として協力と調整が行えるよう、今度は欧州委員会が主導しています。この新たなアプローチでは、インダストリー4.0の技術的進展を基盤にしつつ、「人間中心/協働」、「サステナビリティ(持続可能性)」、「レジリエンス(柔軟性と回復力)」の3点が狙いとなります。最初の「人間中心/協働」とは、技術で人を置き換えるのではなく、人の能力を補完し、協働することを目指しています。技術を活用しつつも人間の創造性や柔軟性を最大限に引き出すことで、カスタム化された製品の提供を目指します。次の「サステナビリティ」では、環境に配慮した素材使用やエネルギー消費の最小化など、地球環境への影響を抑え、高品質な製品の製造を目指します。そして3点目の「レジリエンス」では、市場変動や自然災害に対し、デジタル技術を駆使することで製造の柔軟性と回復力を強化します。このように次世代の製造では、人間中心で環境保全への配慮が重視されています。例えば、ロボットはこれまで安全のために人と離れた場所で作業することが一般的でしたが、次世代製造ではコボット(協働ロボット)が人と同じ場所で協力しながら作業を行うことになります。日本のものづくりにとってインダストリー5.0とは
インダストリー5.0が狙いとする「人間中心/協働」、「サステナビリティ」、「レジリエンス」の実現は日本のものづくりの課題でもあります。企業ブランドや企業価値の向上が求められる日本の製造各社にとってこれらの実現は不可欠であり、積極的な対応が求められています。例えば、カーボンニュートラルや資源の効率的活用は、企業価値向上の前提となります。地震や豪雨など自然災害の多い日本では不測の事態への迅速な対応力や回復力の強化が求められます。さらに、日本の製造業の海外売上比率は昨今では約6割に達し、その割合をこれからも年々増やしていくことが求められています。販売対象の海外市場には、インダストリー5.0に取り組むEU諸国を始めとして、環境規制が厳しく、持続可能な製造プロセスを求める地域が増えていきます。日本のものづくりにとって、インダストリー5.0導入は、これらの規制に適合し、新たな市場への参入やビジネスを拡大していく上で不可欠となります。海外競合の後塵を拝することなく、積極的に対応を
インダストリー5.0には、欧州の製造企業だけではなく、中国や米国の企業も注目し、既に世界的な広がりを見せています。インダストリー4.0では、各先進国が新興国への影響力争いを繰り広げました。同様に、新たな産業革命がグローバルで浸透していくにつれて、世界をリードし、標準となることを狙って、直ぐに覇権争いが始まります。標準を決めることができれば、より自国の産業や技術に適した環境を整えることができ、技術革新でリーダーシップをとれれば、グローバル競争で優位に立てるからです。しかしながら、スマートファクトリーのベストプラクティスとも言える、WEF(世界経済フォーラム:World Economic Forum)のGlobal Lighthouse Networkとして認定された先進工場の数を見ると、日本は中国、欧米各国と差が開いています。
 図表2:WEF Global Lighthouse Network認定工場数
図表2:WEF Global Lighthouse Network認定工場数
(WEF HP内の工場リストを基に、工場の属する企業本社の国別で集計)
(クリックして拡大できます)
※参考:スマートファクトリー、インダストリー4.0についての過去記事
スマートファクトリーで成果を出すには
https://kobelcosys-dev.demo.iqnet.co.jp/column/monozukuri/20220601/
スマートファクトリー推進の鍵は“標準化と横断”
https://kobelcosys-dev.demo.iqnet.co.jp/column/monozukuri/20240101/
スマートファクトリーで成果を出すには
https://kobelcosys-dev.demo.iqnet.co.jp/column/monozukuri/20220601/
スマートファクトリー推進の鍵は“標準化と横断”
https://kobelcosys-dev.demo.iqnet.co.jp/column/monozukuri/20240101/
2025年3月
ITの可能性が満載のメルマガを、お客様への想いと共にお届けします!
Kobelco Systems Letter を購読