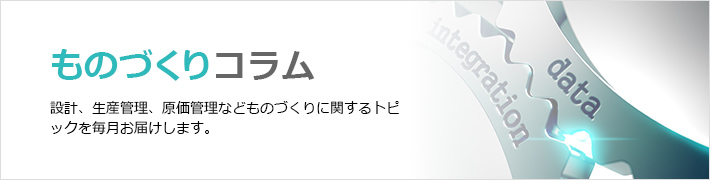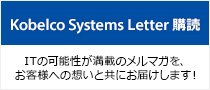2020年11月01日
製造現場のIoT活用について④
~人・物の動きを計測する、ビーコン・RFIDの活用~
今回は、『人・物の動きを計測する、ビーコン・RFIDの活用』として、人や物の動きをIoTで測る方法と、活用事例、利用上の注意点について紹介します。
製造現場では、原材料、中間製品、製品が整然と流れていきます。また、現場の作業員の方も、生産設備を見回り、段取り、段替え、調整と忙しく動かれています。 このように時々刻々移動するものや人の動きを測る手段として、ビーコンやRFIDがあります。 ビーコンは、定期的に指定した強度の電波で固有の識別符号を周りに発信します。ビーコンの受信機がこの電波を受信し、識別符号を読み取ります。これで、固有の識別符号を持ったビーコンがどの受信機の近くにあるのかがわかります。
RFID(NFC)は皆様がすでにお使いの交通系カード、マイナンバーカードで利用されています。 RFIDを受信機に近づけると、RFIDの内容を受信機が読み取ります。ビーコンと同様にどこを通ったかがわかります。
- 人、物、フォークリフト、無人搬送機など移動体の位置情報や属性情報を簡単に収集する方法として、ビーコンやRFIDを活用することができます。
- ビーコンやRFIDには、あらかじめ識別情報(ID)を記録することができ、この識別情報を発信します。
- ビーコンには、温度、湿度、圧力センサーデータを合わせて送信するものもあります。
- ビーコンやRFIDを移動体に貼り付け、スマートフォンや基地局で読み取る場合と、ビーコンやRFIDを固定場所に貼り付けておいて、近くを通過したスマートフォンや基地局が固定場所情報を読み取る場合があります。
 図1:ビーコン、RFID(NFC)で測れるもの
図1:ビーコン、RFID(NFC)で測れるもの
(クリックして拡大できます)
ビーコンとRFIDについてもう少し詳しく紹介します。 表1にビーコン、RFIDが使用する電波や特性をまとめています。
表1:ビーコン・RFIDの特徴
 (クリックして拡大できます)
(クリックして拡大できます)
- RFIDには、電池を内蔵し電波を発信するアクティブ方式と、読み取り装置からの電波により自励発電し電波を発信するパッシブ方式があります。パッシブ方式では、数cm内での通信が可能です。
- NFCは、RFIDの一つの規格です。交通系カード、マイナンバーカードはこのNFC方式を使っています。
- RFIDのうち、電波を利用するもの(433MHz,920MHz)は、電波利用申請が必要です。
- ビーコンは、電池を必要とします。電波の発信頻度、強度の設定によりますが、1年~5年で電池交換が必要です。
- 電池交換、RFID識別情報とその他システム情報(品番・製番等)との紐づけ、電波が届かない範囲の取り扱いなど、運用設計が重要です。
では次に、ビーコン、RFIDを活用すればどのようなことができるのか、活用事例を見てみましょう。 一番目の事例は、工場内の在庫管理の例です。
- ビーコンやRFIDを現品に添付することで、物がどこにあるのかを人手を介することなく収集できます。
- ビーコンやRFIDの受信局を置き場に設置し、受信局からの電波到達範囲にあるビーコンやRFIDが保持するデータを一斉に読み取ることができます。
- 梱包されたものでも、電波が届けば応答します。都度開梱して現品を確認する手間がいらず、一斉に自動で在庫場所を収集します。
-
電波が届く距離は、ビーコン、または受信局で設定します。
置き場の中心に受信局を設置し、電波到達範囲に入ったときや出たときのデータを記録すると、中間在庫、仕掛時間データを収集できます。
 図2:ビーコン、RFIDによる工場内在庫管理の例
図2:ビーコン、RFIDによる工場内在庫管理の例
(クリックして拡大できます)
二番目の活用事例は、加工工場での人と工作機械の協働の最適化です。
- 工作機械がチョコ停をしたとき、オペレータがいかに早く復旧させるかが、工作機械の稼働率に影響します。
- チョコ停にも、プログラムストップやオペレーショナルストップなど、あらかじめ停止を予測できオペレータが待機できる場合と、アラーム停止のように予期できない停止があります。
- オペレータが予期できるチョコ停に対して、時間ロスなくオペレータが対応できるようにするためには、オペレータの動線も管理の対象にしなければなりません。
- オペレータは、加工品の段取り、据え付け、加工調整、加工確認、段替えを複数の機械掛け持ちで忙しく作業しています。どの作業に時間を取られていて、どこで手が足りなくなっているのかを可視化して、改善策をTQCで改善できる仕組みが必要です。
 図3:人と工作機械の協働の最適化例
図3:人と工作機械の協働の最適化例
(クリックして拡大できます)
三番目の活用事例は、工場内の搬送・運搬の無駄改善の取り組みです。
- 「手待ちの無駄」、「運搬の無駄」を改善するには、物の動きや搬送機の動きを情報化することが必要です。
- フォークリフト、搬送台車や天井クレーンの動きを情報化することで、 「運搬の無駄」を可視化することができます。
- 人や物の動きの両方を情報化することで、「手待ちの無駄」を可視化することができます。
- 可視化できれば、TQC活動で課題を共有し、解決策を検討することができるでしょう。
 図4:工場内の搬送・運搬の無駄改善
図4:工場内の搬送・運搬の無駄改善
(クリックして拡大できます)
ビーコンも、RFIDも電波を使っているために電波の乱反射、遮断されてしまうとうまく機能しないという欠点もあります。電池切れ、電波が届かない、そういった異常事態を想定した運用方法を検討した上での導入が必要です。 今回は、ビーコン・RFIDといった電波を用いたもの、人の位置情報を測り活用する事例について紹介いたしました。
次回は、『スマートフォン・タブレットの活用』についてご紹介いたします。
※当社ホームページに、IoTプラットフォームサービスの紹介資料を掲載しています
https://kobelcosys-dev.demo.iqnet.co.jp/solution_service/detail/kits/
※このコラムに対するお問い合わせフォーム
https://kobelcosys-dev.demo.iqnet.co.jp/inquiry/other/
2020年11月
ITの可能性が満載のメルマガを、お客様への想いと共にお届けします!
Kobelco Systems Letter を購読